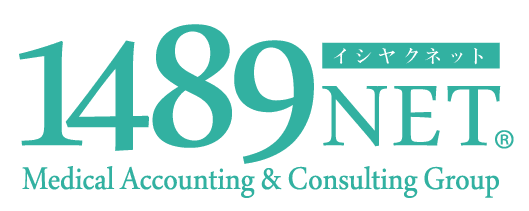開業医師インタビュー
なかうずらクリニック後藤 芳章 院長
- 住所
- 岐阜市中鶉7丁目72-1
- URL
- https://nakauzura-clinic.jp/
- 開業日
- 2020年11月2日
- 診療科目
- 内科・循環器内科・呼吸器内科・小児科・歯科
- 開業支援実績
- こちらからご覧になれます
岐阜県岐阜市、前面4車線の見通しの良い大通りに、2020年11月「なかうずらクリニック」が開業した。循環器内科をご専門とする後藤芳章院長が内科を担当され、奥様である後藤憂子副院長が歯科を担当される、医科歯科連携のとれるクリニックである。
開業地探しに4年もの年月を割いた後藤先生は、万全の調査を経てこの地でご開業された。なかうずらクリニックのご開業はコロナによる混乱の真っ只中であったが、好立地ゆえ患者数は右肩上がりに伸び、開院から1年を過ぎて2年目に突入した今、後藤先生は「忙しすぎて大変」と語った。
岐阜の医療に貢献
糖尿病を患い入退院を繰り返していた父親の姿を見ていた後藤先生は、病気の治療はもちろん、慢性疾患の管理がどれほど大変なことか幼いながらに実感していた。そのような出来事もあり、高校で将来の進路について考えた時に「人として生まれたからには、誰かの助けになるような仕事がしたい」と決心し、医師の道を志すようになる。
故郷である岐阜県に恩返しをしたいと考えた後藤先生は、岐阜大学医学部をご卒業後は岐阜県内の病院で医療に従事し、地元の医療に貢献してきた。専門領域である循環器内科においては「他県に遅れをとることなく、最新の医療を提供したい」という考えのもと、ハイブリッド手術室の整備や経カーテル的大動脈弁留置術などを岐阜県内で初めて導入し、積極的に先進医療を提供し続けた。
「勤務医として17年間診療に従事する中で、やりきったと思うと同時に、もっと地域の人たちと心が触れ合うような診療がしたいという思いも芽生え始めました。病院では多数の手術を行っていましたが、それよりも地域の人に密着した、患者さんと向き合う診療をしたかったのです。また、歯科医師は独立開業される方が圧倒的に多く、歯科医師である妻もゆくゆくは開業したいという夢を持っていました。それならば一緒に開業して、医科歯科連携のとれるクリニックにしようと思い、夫婦での開業を志したのです。二人とも同じ方向を向いて開業準備を進めることが出来たので良かったです」
妥協しない物件選び
開業する為には金融機関から融資を受けることになり、その返済を考えるとなるべく早いうちに開業をし、働ける期間を長くした方が良い。そう考えた後藤先生は、41歳までに開業するという目標を掲げた。そうして始まった後藤夫婦の開業準備であったが、開業地探しは難航を極める。開業において立地の選定が何よりも重要だと考えていた後藤先生は、開業に向けた準備期間5年のうち、4年間を開業地探しに充てたという。
「開業の候補地を探すために、それまでコンサル会社や薬局、税理士、銀行など、5社以上のあらゆるところに相談をしました。しかしなかなか良い開業地と巡り合えず、中には診療圏調査(その地域で開業をしたとして、一日に何人の患者が来るか推定するもの)を全く考慮していない土地を勧めてくるコンサルタントもいました。そんな中出会ったのが、医歯薬ネットさんです。病院に届く1489MAGAZINEは目にしていたのですが、サポートエリアは東京や大阪の中心部だけだと思っていました。しかし中部地方も開業支援の対象エリアだと知り、妻とともにセミナーに参加することにしました。その時に森田会長が仰っていた『10年経ったら普通の医者』という言葉が、41歳で独立開業しようと思っていた自分と共感するところがあったので、医歯薬ネットさんに頼んでみることにしたのです」


後藤夫妻の開業をサポートすることになった中部支社のコンサルタントと共にまずは開業希望エリアの再確認を行った。開業地の条件として往々にして話題に上がるのが「駅チカ」であるが、後藤先生はあえて駅から離れる郊外に注目した。
「岐阜駅の駅周辺は既に多くの内科クリニックがありましたし、ここは若者の流入が少なく、高齢者が多く住む地域ですのでドーナツ化現象も進んでいます。そこで私は居住人口の増加が期待できない駅チカ物件ではなく、車での交通の便が良い郊外での開業を希望しました。戸建てになるので、テナント開業に比べれば土地代や建築費など初期費用は高くなりますが、集患が望める場所であれば問題ないと考えました。医療業界では、根拠(エビデンス)に基づいた医療を行うことが大切だという考えがありますが、物件探しもそれと同じで、『ここなら成功する』というエビデンスを揃えて一軒一軒慎重に検討することが非常に大切だと思います」
物件探索を行った医歯薬ネットからはトータルで30件ほどの候補地を紹介し、その都度診療圏調査の精査や現地視察を行い、開業地を吟味してきた後藤先生。
「推定される患者数を見て比較すれば良いという単純な話ではありません。例えば立地面では、診療圏調査の地図上に大きな川があったら、川の向こうの地域からは患者が来ないかもしれないと予想する必要があります。 また、開業希望地の周辺に競合クリニックがあるのかどうかも注目します。近い距離に同じ内科を作ったとしても、地域への社会貢献性は低くなってしまいますから。せっかくなら、他に誰もいないところで開業した方が良いと思います。また、実際に自分の目で候補地を見に行くことで、物件の周辺状況であったり人の流れを理解することが出来ます。紙媒体の物件情報だけでは分からなかったことが分かるので、現地を見に行くことがお勧めです」

そして後藤夫妻が開業地として選んだのは、支店統廃合で更地になることが決まっていた銀行の跡地であった。ここは周辺1キロ圏内に内科の競合クリニックが1軒もなく、診療圏調査の結果が抜群に良かったのだ。
「医歯薬ネットのコンサル担当の方から、ここで失敗するならどこでも失敗しますよ、と言われました。それもそうだと納得するくらい、ここの診療圏は良かったのです。
また、医歯薬ネットさんは地域の住民の方々にヒアリング調査もしてくださいました。地域住民の方々は今どこの内科に通われているのか、近隣にクリニックが出来るとしたら何科がいいか等ヒアリングしてくださり、地元の方のリアルな意見を集めることが出来ました。 結果的に、この地には内科クリニックを必要としている方が多くいるという証拠を揃えてくださり、実際の内覧会でも『この周囲にはクリニックがないからありがたい』というお言葉を多数いただくことができて、やはりここでの開業は間違いなかったと確信しました」
うなぎ上りの患者数
コロナ禍にもかかわらず、土日2日間で行った内覧会には約700名もの方々がクリニックを訪れて周辺住民からの注目度の高さが伺えた。
しかし開院直後は、手洗い習慣やマスクの着用が当たり前となった中で通常の風邪患者が少なく、患者数が伸び悩む日が続いていたという。
「ゆっくりとした立ち上がりではありましたが、そんな中でもコロナ対応に励んでいました。するとコロナ診療に熱心に取り組むクリニックとして新聞やNHKの取材を受ける機会があり、そこで認知度が高まったのか患者数が増えていったのです。 三ヶ月経つ頃には、事業収支計画書で設定していた患者数を倍以上も上回るようになって、忙しすぎて大変という状況になりました。特にワクチン接種が始まった時は40台分ある駐車場がいっぱいになってしまうほど多くの患者さんが来院され、接種が落ち着いた今も、100人近くの患者さんがいらっしゃる日もあります」
「実はレイアウトを決める際、医歯薬ネットさんから待合室はもっと広く作っておいた方がいいと言われていました。しかし当時の私は、そんなに大きくする必要は無いだろうと思って結局そのままにしたのですが……今思えば、なぜもっと大きくしなかったのだろう、と。素直に医歯薬さんの言うことを聞いておけばよかったですね」
内科の午前診療と午後診療の間の時間を活用して訪問診療も行っている後藤先生は、勤務医時代よりも今の方が格段に忙しいと話す。嬉しい悲鳴をあげる日々の中、後藤先生の頭には既に次のステップが浮かんでいた。
「今までは内科という大きな枠でやってきましたが、今後は私が専門としている循環器内科の領域である、心臓リハビリテーションを行いたいと思っています。これは開業前から想定していたことなので、心臓リハビリテーション専用の部屋も予め設けていま した。病院での勤務経験を活かすためにも、循環器内科の特色をもっと前面に出していければ良いです」
今だからこその開業
「開業で大切なことは、開業地選定で妥協しないことと、信頼できるコンサルタント会社を選ぶことです。ひとえにコンサルタント会社と言っても、会社によって質や実力は大きく変わってきます。複数社で比較検討した上で、自分と合う会社を見つけることが大切だと思います。 今開業を考えられている先生方の中には、世間的に受診控えの風潮もあるので今は開業するのをやめておこうと思う方もいらっしゃるかと思います。しかし自分が働ける年齢は決まっていますし、ご自身の年齢と、開業にかかる資金の返済期間などを加味して開業時期は考えた方が良いかと思います。 退去も増えるコロナ禍だからこそ出てくる物件があるかもしれないし、開業を躊躇う人がいるからこそ、逆に今が狙い目という見方もあります。このご時世だからこそ、思い切って開業に向けた準備を始めてみてはいかがでしょうか。開業してみたら毎日想像以上に忙しいですが、やりがいを感じています」(掲載内容は、取材当時のものとなります)
クリニックのレイアウト

Doctor’s Profile
【ご経歴】
・平成17年 岐阜大学医学部医学科 卒業
岐阜県総合医療センター 臨床研修医
・平成10年 岐阜県総合医療センター 循環器内科
・平成20年 平成紫川会 小倉記念病院 循環器内科
・平成21年 岐阜県総合医療センター 循環器内科
・平成24年 朝日大学村上記念病院(現 朝日大学病院)循環器内科助教
・平成24年 岐阜県総合医療センター 循環器内科
・平成29年 岐阜県総合医療センター 循環器内科 医長
・令和2年 なかうずらクリニック 開院
【所属学会・資格など】
日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本脈管学会専門医、日本心血管インターベンション学会認定医、日本心臓リハビリテーション学会心臓リハビリテーション指導士、日本ステントグラフト実施管理基準委員会、胸部/腹部ステントグラフト指導医、経カテーテル大動脈弁置換術認定制度指導医、ICLS認定インストラクター、JMECC認定インストラクター、第二種電気工事士 ほか
お問い合わせ
・ご相談
まずはお気軽にお問合せください