2025年3月28日
【クリニック開業】マイナ保険証の導入で気を付けるべきポイントとは?(後編)
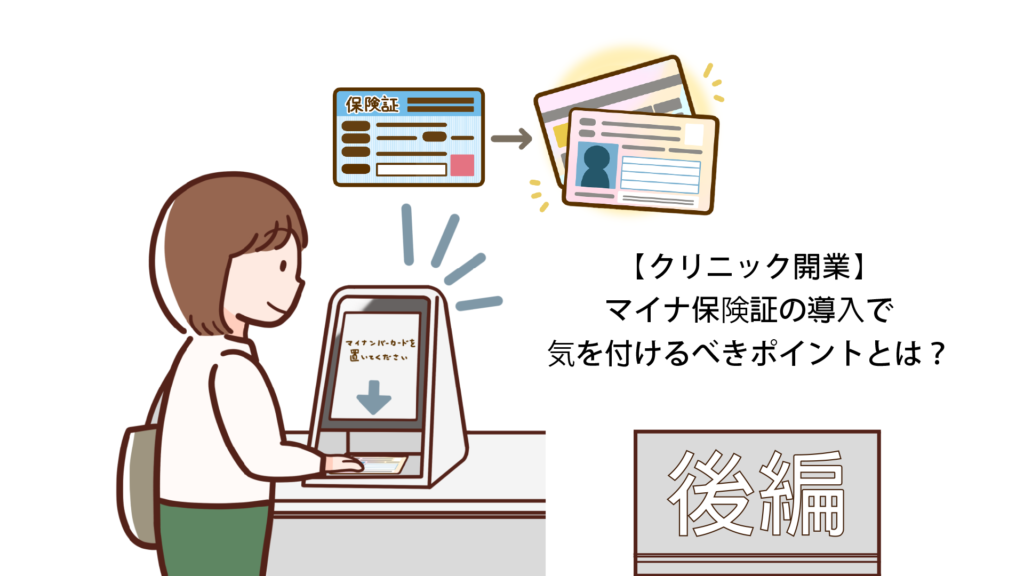
皆さんこんにちは、医歯薬ネットです!
今回は、前編に引き続き「マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)」に関してのお話です!
「マイナ保険証の導入で気を付けるべきポイント」のうち、後編(本ブログ)では「開業後」、主に運営面で気を付けるべきポイントをお話します。

(目次)
1.マイナ保険証のしくみって?オンライン資格確認とは?
2.【マイナ保険証】クリニック「開業時」に気を付けるべきコト(設備投資面)
3.【マイナ保険証】クリニック「開業後」に気を付けるべきコト(運営・診療報酬面)
(※なお1.および、2.は「前編」にてお話ししました。前編はこちらよりお読みいただけます。)
本編では3.以降についての記事となります。
—――――――――――—――—――――――――――—――――――――――
開業後に注意すべきこと、それは「診療報酬」についてです。
まず、診療報酬に関して簡単にご説明します。
診療報酬は、自己負担分(原則3割※年齢や所得に応じて異なります)として患者さんから、残りは加入している医療保険者から、それぞれ医療機関等に支払われます。(参照:なるほど診療報酬!|国民のみなさまへ|日本医師会)
なお、診療報酬の点数は、1つ1つの診療行為ごとに厚生労働大臣によって細かく決められています。
診療行為に対する価格は、その行為ごとに決められた点数を基に「1点=10円」として計算されます(例えば、初診料291点ですと2910円になります)。
(参照:なるほど診療報酬!|国民のみなさまへ|日本医師会)
そして、「診療報酬」と密接にかかわってくるのが、「施設基準」です。
下記は東京都医師会HP([3] 施設基準や帳票類等 | 総論 | 「新規開業医のための保険診療の要点 | 公益社団法人 東京都医師会公益社団法人 東京都医師会)より抜粋したものです。
゛厚生労働大臣が定めた医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等の基準で、一部の保険診療報酬の算定要件として定められています。
施設基準は多数の診療報酬に設定されていますので、請求の際には該当点数の算定上の要件まで確認することが必要です。”
なお、注意点として下記の通り案内がされています。
<注意点>
基準を満たすことが条件とされていても、届け出までは必要とされていない項目もありますが、診療報酬の請求に当たってはきちんと確認が必要です。
診療報酬の注に「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た医療機関」とある項目を算定するには、その医療機関は該当する基準要件を満たした上で、地方厚生局(東京都では関東信越厚生局東京事務所)に届け出を行い受理されていることが条件となります。”
(参照:東京都医師会HP([3] 施設基準や帳票類等 | 総論 | 「新規開業医のための保険診療の要点 | 公益社団法人 東京都医師会公益社団法人 東京都医師会)より)
分かりやすく言うと、医療機関が収入として得る「診療報酬」には、(保険)診療行為を行えばそれだけで算定が可能なもの(報酬として得られるもの)がある一方で、
”「施設基準」を満たして初めて得られるもの(報酬)“ があるわけですね。
その中には「届出」が必要な施設基準が存在するということです。
「診療報酬」「施設基準」に関しての前置きを踏まえたところで・・・
今回のテーマ「マイナ保険証」と密接に関係するのが、医療DX推進体制整備加算です。
医療DX推進体制整備加算は、診療報酬の算定方法について令和6年度診療報酬改定で新設された制度です。所定の施設基準をみたす医療機関は、本来請求できる診療報酬に上乗せて報酬を得ることができます。
では、医療DX推進体制整備加算の施設基準を確認してみましょう。
(※なお下記記載の情報は2025年3月28日時点での情報となりますので、診療報酬等の最新情報については厚生労働省HP(診療報酬関連情報|厚生労働省)より適宜ご確認いただきますようお願いいたします。)
【医療DX推進体制整備加算1~6】
(参照:厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」該当頁:21~23頁・第1の9)
当該施設基準に関して、概要は以下の通りです。
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)医師・歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
(4)電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。(加算1~3のみ)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
(8)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
※なお、下記は厚生労働省より公表されている当該加算についての概要(抜粋)です。
掲載ページ:令和6年度診療報酬改定について(令和6年4月以降改正について)|厚生労働省
(※「第1 改定の概要」欄のURLよりご確認いただけます。)
マイナ保険証と関わってくる要件は、(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること です。
今回(1)~(5)、(7)および(8)に関しての詳細な説明は割愛しています。
(※「新規開設」の場合、医療機関(開業する先生方)側で当施設基準のために整備するものというより、開業準備として整備していくものが大半のためです。これから新規開設する医療機関においては、開業の際に導入する医療機器(電子カルテ等)メーカー、HP広告業者等へ念のため一度ご相談いただくのがよいでしょう。)
※なお特筆すべき注意点としては、下記が挙げられます。
・(4)電子処方箋の導入に関しては、導入の可否で点数が変動します。
導入した医療機関は当該加算1~3、導入していない医療機関は加算4~6のうち充足する要件に応じて算定が可能となります。
・(5)電子カルテ情報共有サービスについては、令和7年9月30日まで「経過措置」期間のため、すべての医療機関について無条件で要件を充足するとみなす「みなし措置」が図られています。
前述の通り、医療機関側での取り組みが大きく影響するのは、
(6)「マイナンバーカードの健康保険証利用の使用実績」についての要件です。
分かりやすく言うと、「マイナ保険証を使って受付した患者さんが多ければ多いほど、高い加算がとれる」というしくみです。
要件詳細は下記の通りです。
(参照:「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」該当頁:21~23頁・第1の9)
※令和7年4月1日から適用となります。
医療DX推進体制整備加算1(医科)12点・・・
医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、45%以上であること。
医療DX推進体制整備加算2(医科)11点・・・
医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であること。
医療DX推進体制整備加算3(医科)10点・・・
医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であること。
【電子処方箋を導入していない医療機関】
医療DX推進体制整備加算4(医科)10点・・・
医療DX推進体制整備加算4を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、45%以上であること。
医療DX推進体制整備加算5(医科) 9点・・・
医療DX推進体制整備加算5を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であること。
医療DX推進体制整備加算6(医科) 8点・・・
タイトル医療DX推進体制整備加算6を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であること。
なお、この「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」に関しては、各医療機関がポータルサイト(医療機関等向け総合ポータルサイト – 医療機関等向け総合ポータルサイト)上で詳細を確認いただけます。
厚生労働省より、「マイナ保険証利用率増加に向けた取り組み」として様々な案内がなされています。
参照:社会保険診療報酬支払基金(情報化企画部・情報化支援部)・国民健康保険中央会(医療保険情報提供等実施機関担当室)HP:共通 – マイナ保険証利用率増加に向けた取り組み
「院内デザイン」、「患者さんに対する周知」等において、マイナ保険証利用促進を意識した取り組みの好事例が紹介されているので、いくつかピックアップしてご紹介します。
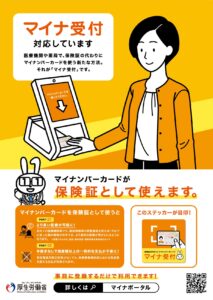
① 受付で一言目に「マイナンバーカードをご利用ください」と案内すること
(シンプルですがやはり効果的なようです・・・!)
② 施設内にメリットを記載したポスターなどを掲載し、患者さんに寄り添った案内をすること
厚生労働省のホームページより、院内掲示物をダウンロードできます!
オンライン資格確認に関する周知素材について
③ 受付のわかりやすいところに顔認証付きカードリーダーと案内ポップを設置
④ 受診時等の持ち物欄や予約画面に「マイナンバーカードをお持ちください」とわかりやすく記載すること
ぜひ参考にしてみてください。
※弊社でご支援させていただいた昨年開業のとある先生は、やはり医療DX推進体制整備加算の見直し等を考慮し、最大限利用率を上げるべく上記取組等を積極的に行っていらっしゃいました。(その甲斐あって、2024年10月・11月・12月における各月のマイナ保険証利用率はそれぞれ50%以上達成したとのご報告がありました。すばらしい・・・!)
※なお、直近のデータとして、2025年2月における全国の「マイナ保険証利用率」は26.62%となっています。(引用元:マイナ保険証利用件数 12月をピークに10%・577万件減少 – 全国保険医団体連合会)
クリニックの取り組み次第では、上記全国利用率より大幅に向上させることも不可能ではないということですね。
なお、医療DX推進体制整備加算を算定するためには、「(様式1の6)医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出書添付書類」の記載・提出が必要です。
提出(届出)は医療機関が所在する都道府県を管轄する厚生局事務所に1部提出することとなっています。
(参考として厚生労働省の一支局である関東信越厚生局HPリンクを置いておきます。→基本診療料の届出一覧(令和6年度診療報酬改定))
今回ご説明している 医療DX推進体制整備加算に関しては、「各様式」項目記載の
「整理番号・1-7/ 施設基準名称・医療DX推進体制整備加算」というところから形式のダウンロード、提出書類の作成ができるようになっています。
※関東信越厚生局の他に、
・東北厚生局
・東海北陸厚生局
・近畿厚生局
・九州厚生局
上記をはじめとした合計8つの地方厚生局がありますので、医療機関所在地を管轄する地方厚生局および管轄事務所をご確認の上、手続きをお進めいただければと思います。(参照:全国地方厚生(支)局の管轄地域)
届出に関する詳細内容は各地方厚生局のHPにまとめられているため、各医療機関管轄の厚生局HPをご参照ください。
なお、「医療DX推進体制整備加算」について提出が必要となる届出書様式を参考までにおいておきます(※2025年3月28日時点の届出書様式となります)。
いかがだったでしょうか?
前編よりご紹介してきた「マイナ保険証」関連の注意点についてまとめると、
開業前
開業に際しては原則義務化のため、「オンライン資格確認」のシステム導入が必要(スケジュール要注意)
→マイナ保険証を患者さんに使ってもらうために必要なシステムの導入ですね。
開業後
クリニック収入up(加算を取る)ためには、施設基準「医療DX推進体制整備加算」を満たす必要がある
→厚生局へ施設基準の届出をして、マイナ保険証利用率の実績を一定程度達成する必要がありました。
前編に引き続き、開業後においても手続書類が多く、流れが複雑ですね。。
医歯薬ネットでは、開業までの一連の流れを熟知したコンサルタントが、
法改定、診療報酬改定等にも沿いながら最新かつ最適な医院開業を実現いたします。
開業後の快適な「開業医ライフ」を見据えたプランの組み立てが可能です。
初めてのご開業でご心配なこと、分からないことも多い先生方が、
万全の態勢で「安心安全な開業」を迎えられるよう、医歯薬ネットは全力でご支援してまいります・・・!


具体的な開業に関するお悩みや条件などは、セミナーご視聴後にご希望に応じて設定する個別面談にて医院開業のプロのコンサルタントに直接ご相談いただけます。
上記バナーをクリックして、お気軽にお申し込みください!
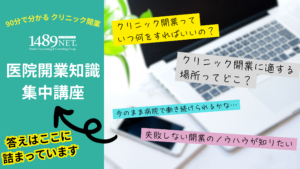
2025年2月28日
90分でわかるクリニック開業!3月よりセミナー内容をリニューアル!
皆さんこんにちは!医歯薬ネットです!医歯薬ネットが週に2回開催している「開業の為のオンラインセミナー」ですが、3月より内…

2024年10月4日
皆さんこんにちは!全国の勤務医の先生方に向けてお送りしている1489MAGAZINE(イシヤクマガジン)には、「起業医 …

2023年5月26日
みなさんこんにちは!医歯薬ネットです。さて、早くも5月最後の金曜日。来週から6月が始まりますね。本日は5月の開業支援実績…